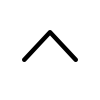活動ブログ
「手でふれてみる世界」ワークショップ
- 高齢者施設・その他
6月22日(日) 佐倉市立美術館4階ホールで、見える人も見えない人も、共に美術作品に手でふれて鑑賞できるイタリアの「オメロ触覚美術館」を取材したドキュメンタリー映画の上映会と、ブラインドコミュニケーターの石井健介氏を講師に迎えて行う触察の鑑賞会を行いました。1日を通して延べ100人近くの方に参加していただきました。
「オメロ触覚美術館」を取材したドキュメンタリー映画は、バリアフリー日本語字幕と音声ガイドのついた上映でした。見える人も見えない人も、聞こえる人も聞こえない人も、一緒に鑑賞できます。まずは、このようなユニバーサル上映を初めて見たという人も多かったのではないでしょうか。劇中、盲目の老夫婦が、子どものようなキラキラとした興味と興奮とともに、 触れることによってアート作品を鑑賞している姿に、私も幸せな気持ちになりました。映画の中で紹介された触察という鑑賞方法と、私たちミテ・ハナソウが行う対話型鑑賞に共通していることは、「ともに鑑賞することを通して相手を知り、友情で結ばれる」ということです。とても印象に残ります。

午後は、ブラインドコミュニケーターの石井健介氏を講師に迎え、触察の鑑賞会を行いました。アイマスクをして、視覚に頼らない鑑賞を体験してみました。「ここはどうなっているんだろう」「素材はなんだろう」とグループで話しながら、五感を総動員して鑑賞します。触察しながらグループの中で交わされる会話も、作品に負けないくらい楽しいものでした。「彫刻を目で見ている時は何も考えていないけど、アイマスクをして彫刻を触っている時はいろんなことを考えた」と感想を話してくれたのは8歳の女の子でした。

最後に「石井健介さん×佐倉市立美術館×ミテ・ハナソウ佐倉」のクロストーク。テーマはこれからの佐倉市立美術館を語る「シン・マチ美術館」。
昨今、「合理的配慮」というキーワードがよく聞かれるようになってきましたが、美術館もちょっとした工夫で、どんな人もミュージアムにアクセスしやすく、そして楽しむことができるようになります。そのためには、設備的なハード面の整備とともに、ソフト面での工夫も大切です。佐倉市立美術館が、「私の町の美術館」として地域の人に愛され続ける美術館となれるよう、ミテ・ハナソウ佐倉も共に考え続けていきたいと思います。そしてこれからも佐倉市立美術館が、子どもにも大人にも、シルバー世代にも、どんな個性の人にとっても、アートにふれることで、楽しい あるいは ほっとした気持ちになれる、そんな 開かれた「私の町の美術館」であってほしいと思います。

ミテ*ハナ じゅんじゅん
<美術館より>
ここ最近、美術館に求められる役割は多様化しています。2022年の博物館法の改正に伴い、従来の「研究」や「展示」にとどまらず、「地域の多様な主体との連携」が求められるようになりました。視覚に障害を持つ方々とのプログラムとしては、これまで10年以上ともに鑑賞の活動を続けてきたミテ・ハナソウ佐倉と、株式会社QDレーザの協力のもと、昨年8月に見えづらさを感じる方と晴眼者の方が一緒に展示室で作品を見る鑑賞会を開催しました。今回の「手でふれてみる世界」の上映会と触察ワークショップは視覚に障害を持つ方との鑑賞会第2弾ということで、小さなお子さんから大人の方まで、幅広い参加者が集い、ともに語り、考える場になったと思います。普段美術館では作品を直接手で触ることは、作品保護の観点から難しいのですが、今回は特別に社会福祉法人空と海さんに協力をいただき、見えるひとも見えない人も、手で直接作品にふれて形や色を想像しました。
私は、美術館は様々な価値観への問いを共有する「公共の思考空間」として機能し得る場であると考えます。佐倉市立美術館はこれからも、多様な価値観のクロスポイントとなるような企画を実施していきます。みなさんもぜひ、ともに考え語りましょう。美術館でお待ちしています!
佐倉市立美術館 学芸員 西川可奈子